
神代和紙復活ストーリー
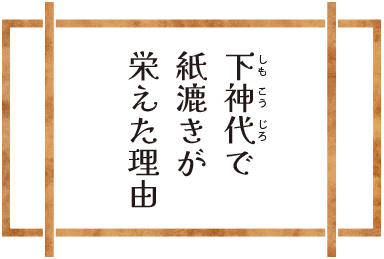
神代(こうじろ)和紙は、岡山県新見市神郷(しんごう)下神代(しもこうじろ)地区で漉かれていた和紙です。岡山県通史に、新見は“帰化人の開いた土地”という意味があると書かれてます。このことから、帰化人によって下神代に早くから製紙の技術が伝わったのではないかと考えられています。
紙は、楮(コウゾ)、麻(アサ)、三椏(ミツマタ)、雁皮(ガンピ)といった植物の靭皮(じんぴ=木の外皮のすぐ内側にある柔らかな部分)が原料。下神代にはこれら植物が自生し、谷から流れる水が豊富で清らか、冬の寒さが厳しいという製紙の条件が揃っていたことで紙漉きが栄えたと言えます。
今でも早春の3月頃になると、近隣の谷川沿いに三椏の花が咲きます。紙漉きが始まった頃からずっと咲き続けていることでしょう。

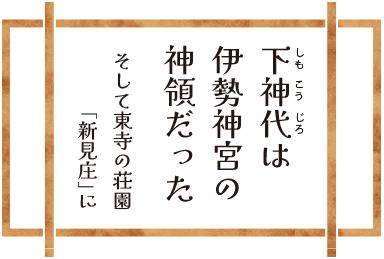
紙漉きの歴史を紐解くと、伊勢神宮(内宮)の神領だった平安時代までさかのぼります。下神代には、地理的に神領家への物資の輸送や市場への輸送や人々の出入りなどに便利なことから「政所(まんどころ)※事務全般を行う場所」がありました。ここから神代和紙は献上品として、伊勢の国へ運ばれていたということです。
中世室町時代になると、伊勢神宮神領である下神代と隣接していた新見の一部地域が東寺(京都)の荘園「新見庄(にいみのしょう)」となります。その後下神代は「新見庄」に吸収され、神代和紙は東寺に献上されるようになりました。
「新見庄」の資料※1に、「公事紙を送れ」という東寺からの催促が頻繁にあったことが記されています。これに答えて「今少し待ってもらいたい」と、詫びの手紙が実に多かったことから、当時の人々が昼夜問わずで紙漉きをしても注文に間に合わなかったのでしょう。それほど神代紙の品質が高かったと言えます。

(とうじひゃくごうもんじょ)」
“古代が飛鳥で代表されるなら、中世を代表するのは新見である”と言われるほど、中世の資料が残っている新見。中でも国宝「東寺百合文書」は京都の東寺に伝えられた、8世紀から18世紀までの約1千年間にわたる古文書群は有名で、東寺の荘園「新見庄」の資料が大量に残っています。庄内では鉄、漆、蝋、紙などの特産物を有し、舟運も開かれていたことが書かれています。
「東寺百合文書」が現在まで残っているのは、和紙に筆と墨で書かれているため長期間の保存に耐えたからだといわれています。そして、中世の紙について研究する上でも貴重な素材ということです。
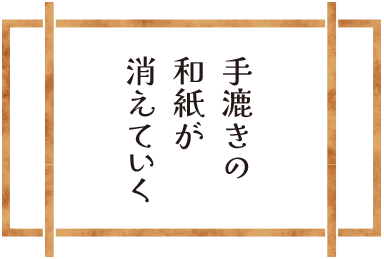
物を紙で包むようになったのは平安時代。鎌倉時代になると、和紙を折り目正しく折って贈答品を渡す「折形礼法(おりがたれいほう)」が武家の教養となりました。折形とは、現代の不祝儀袋や熨斗紙のルーツ。物を心を込めて包み渡す由緒正しき礼法の一つです。
江戸時代に入って和紙が安く大量に出回るようになると、「折形」は庶民の生活に溶け込み、赤飯や餅に添える塩やきな粉を紙で包んで添えるという使われ方が日常になっていきました。和紙を折って物を包む文化は昭和初期まで続きますが、欧米文化が入ってきた戦後急速に生活から姿を消していきます。今では贈答品を包んで熨斗紙を貼るのは業者任せ。祝儀、不祝儀袋やポチ袋でさえ100均で間に合う時代です。
思えば、折形に限らず、日本人の暮らしには常に和紙がありました。襖や障子、提灯、傘、掛け軸、扇子や団扇。これらの需要が減っていった理由は、生活様式の西洋化だけでなく、明治期の文明開化も要因の一つです。切手や新聞や雑誌の大量印刷が本格化。印刷向きの洋紙が輸入され、早く大量に紙が漉ける機械の導入が進み、安価な洋紙に押され、和紙は衰退の一途をたどることになります。
手漉き和紙の需要が少なくなると、当然後継者も少なくなります。使う人が少なくなり、収入を得ることができない産業に若者の参入は難しくなります。次第に製紙業の廃業が進み、神代和紙も姿を消していきました。

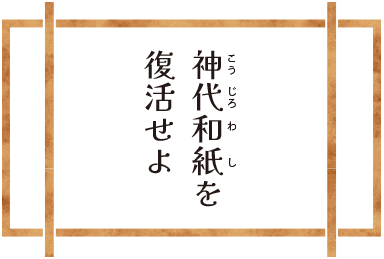
時代は進み、ふるさと創生事業真っ只中の1990(平成2)年。当時の阿哲郡神郷町(現新見市神郷)は、昭和中頃まで精米や製粉に活躍していた水車と、一度は途絶えた神代和紙を復興し、かつ地域の活性化のために「日本一の親子水車(現在は親子孫水車)」と「紙の館」を下神代に整備しました。これらがある一帯を「夢すき公園」とし、地域内外の人的交流の場にすることになりました。余談ですが、夢すき公園には、下手にある10町歩ほどの水田に水を引く水路が通っていて、その水路を改修、活用することで水車が回っています。
ここからは、神代和紙の復興に携わり、現在も保存会で紙を漉いている忠田町子さん自身のことばで、当時から現在までの道のりをたどってもらいます。
オープン当時は、男性2名が紙漉き、女性2名が食堂や土産物を担当していました。館長さんは、お父さんの代からこの地方のミツマタを買い集め、地域の4~5人を雇って皮むきをし、真庭市久世や鳥取県青谷に運び商売をしていた方です。和紙についての知識はあったと思いますが、私をはじめ他の人は、全くの素人でした。それが、紙の館オープンと共に和紙づくりに出会ったのです。これは運命の出会いだと思っています。
当時新見市には、ひたすら紙漉きを続けておられた「高尾和紙」の赤木浦治さんがいらっしゃいました。私たちは赤木さんに紙漉きの技術を一通りご指導していただき、神代和紙復活の船出をすることができたのです。
私たちは、昔ながらの道具を使い、昔ながらの漉き方で、伝統の紙漉きをスタートしましたが、二尺×三尺(一尺=30.3㎝)の大きな桁(けた)に竹の簀(す)をはめた道具を使う「流し漉き」はなかなか難しく、不器用な私にはできそうにないと思っていました。しかし、先に取得した方の漉き方を見たり、和紙の産地の見学に行くうち、「古代技法がやりたい」と強い願望が湧いてきたのです。自分には手の負えないと思っていた紙漉きも、一生懸命練習を重ねていくことで“紙”になり、あの時の感動は今でも忘れられません。それからは、少しでも良い紙を漉けるようになりたいとの一心で、毎年冬になると紙漉きに励みました。
紙の館の歩みを振り返ると、管理者が変わったり、休館のため2~3年漉けない年もありました。一方で和紙を買ってくださる方もあり、たとえ少量でも“売れる”という経験が励みとなり、今日まで続けてこられたのだと思います。心を込めて漉き、皆さんに使っていただくことが大切です。神代和紙の魅力は、光沢があり、素朴で手触りが良く軽くて柔らかいことです。長期の使用でも破れることなく強いので、もっと多くの方に知ってほしいのです。
私もだんだん歳を重ねてまいりました。振り返ってみると、30年以上の長きに渡り、ここで紙を漉き続けてこられたことは、私にとって何よりの幸せです。神代和紙を絶やすことなく誰かが引き継いでくれることを願っていたところ、平成26年から近所に住む土屋くんが、翌年から仲田さんが原料づくりから手伝ってくれるようになりました。仲田さんは、京都からおばあちゃんの住む神代に移住しての参加です。二人とも私の孫と同年代で、とても熱心に取り組んでくれました。和紙は、紙になるまで多くの工程があり、ひとつでも手を抜くと良い紙にはなりません。知識も技術も向上するよう、お互い切磋琢磨している姿を見ると頼もしく思います。
神代和紙を継承してくれる若い世代が、希望を持って取り組み、和紙を広めていくため、平成28年「神代和紙保存会」ができました。私たち漉き手だけでなく、様々な技術やアイデアを持つメンバーも加わり今日に至っています。今は、できるだけ長く紙漉きをすることが私の願いです。

神代和紙は、「紙の館」建設に取り組んでくれた行政と、技術を守り続けてきた先人の努力で復活することができました。ですが、皮肉なことに、神代和紙復活に尽力してくれた赤木氏の「高尾和紙」は後継者がおらず消滅してしまいました。実は高尾和紙は、歴史をたどれば神代和紙から分岐した技術です。このことから、神代和紙の紙漉き技法は、絶えることなく受け継がれてきたといえるかもしれません。
